投稿日:2025.8.22
歯ぐきが下がる歯肉退縮とは?
みなさま、こんにちは!
東京八重洲キュア矯正歯科です。
「最近、歯が長くなったように見える」「冷たいものがしみるようになった」そん
な症状を感じている方は、 歯肉退縮(しにくたいしゅく) が起きている可能性が
あります。この記事では、歯肉退縮の症状や原因、矯正治療中の注意点、そして日
常生活でできる予防法まで、わかりやすく解説します。
目次
歯肉退縮って何?

歯肉退縮とは、歯を支える歯ぐきが後退し、歯の根元が見えてくる状態を指します。
加齢による自然な変化としても見られますが、若年層でも発症することがあります。
見た目の変化があるだけでなく、知覚過敏や虫歯などのトラブルのリスクも高まり
ます。特に初期は痛みなどの自覚症状がほとんどなく、気づかないうちに進行して
しまうことが多いため、早期発見と日常的なケアが重要です。
歯肉退縮によって生じやすいトラブル・症状
歯ぐきが下がると、以下のような症状が現れることがあります。初期は自覚しにく
いものの、そのまま放置してしまうと症状が進行し、歯の健康に深刻な影響を及ぼ
す可能性があります。
①知覚過敏になる
知覚過敏とは、「冷たいものがしみる」「歯ブラシが触れると痛い」など、ちょっ
とした刺激で歯に不快な痛みを感じる状態です。歯肉が下がり、歯の根元が露出す
ると、本来エナメル質に覆われていない象牙質がむき出しになり、刺激が神経に伝
わりやすくなります。そのため、知覚過敏の症状が起こりやすくなり、日常の飲食
や歯磨きで痛みを感じることが増えることがあります。
②歯が長くなって見える
歯肉退縮の特徴として、歯が長くなったように見えたり、歯と歯の間にすき間があ
いたりするため、三角の黒いすき間が目立つ「ブラックトライアングル」が生じる
こともあります。また、歯と歯ぐきのバランスが悪くなり、老けた印象に見えてし
まうことがあります。
③食べ物が挟まりやすくなる
歯ぐきの位置が下がると、歯と歯の間にすき間が広がり、食事のたびに食べ物が詰
まりやすくなります。特に繊維質の食材や肉などは残りやすく、違和感や不快感の
原因になるだけでなく、虫歯や歯周病のリスクも高まります。
④歯周病が悪化しやすくなる
歯ぐきが減って歯の根元が露出すると、歯と歯ぐきの境目にすき間ができ、汚れや
細菌がたまりやすくなります。この部分は歯ブラシの毛先が届きにくいため、丁寧
に磨いているつもりでもプラークが残りがちです。細菌の増殖が続くと、歯ぐきの
腫れや出血、歯のグラつきといった症状が悪化する恐れがあります。歯ぐきがすで
に下がっている場合は歯周病が進行している可能性が高いため、早めに歯科医院で
の診断と治療を受けることが大切です。
腫れや出血、歯のグラつきといった症状が悪化する恐れがあります。歯ぐきがすで
に下がっている場合は歯周病が進行している可能性が高いため、早めに歯科医院で
の診断と治療を受けることが大切です。
⑤虫歯のリスクが高まる
本来、歯ぐきに守られていた象牙質がむき出しになると、エナメル質よりも柔らか
く、酸に弱いため、プラークや細菌が付着しやすく虫歯になりやすい部分です。特
に歯根にできる虫歯は進行が早く、気づかないうちに歯に大きな穴があいてしまう
ケースも少なくありません。
歯肉退縮の原因
①強すぎるブラッシング
毎日の歯磨きはお口の健康維持に欠かせませんが、力を入れすぎたブラッシングは
かえって逆効果になることがあります。過度な力で磨くと、歯ぐきを傷つけてしま
い、歯肉退縮の原因になる可能性があります。また、強すぎるブラッシングを続け
ていると、歯ブラシの毛先がすぐに開いてしまい、細かい部分の汚れが落としきれ
ず、毎日磨いているにもかかわらず虫歯や歯周病が進行してしまうこともあります。
②歯周病
歯周病は歯肉退縮が起こる最も多い原因の一つです。歯周病の症状が悪化すると、
歯ぐきの炎症だけでなく、歯を支えている歯周組織が破壊され、歯茎の位置が下が
る原因となります。さらに進行すると歯がグラグラと動き出し、最悪の場合、抜け
落ちてしまうことがあります。歯周病による歯肉退縮を防ぐためには、毎日のセル
フケアに加えて、定期的な歯科検診やメンテナンスが重要です。進行の程度によっ
ては、歯科医院での治療が必要になります。口臭が強くなったり、ブラッシング時
に出血しやすくなったりする症状が気になる際には、早めに歯科医院を受診しま
しょう。
③口腔ケアが不十分
毎日の歯磨きが不十分だと、歯垢(プラーク)という細菌のかたまりが口の中に残
り、歯ぐきが腫れたり炎症を起こす原因になります。時間がたつと歯垢は硬くなっ
て歯石になりますが、歯石はザラザラして汚れがつきやすく、通常の歯磨きでは取
り除けません。歯石を放置すると歯周病のリスクが高まるため、歯科医院で定期的
にチェックとクリーニングを受けることが大切です。
④歯ぎしり・食いしばり
歯ぎしりや食いしばりは、無意識に強い力が加わることで、歯にヒビが入ったり、
歯ぐきが下がる「歯肉退縮」の原因になることがあります。歯のすり減りや顎の痛
みを感じる場合もあり、特に就寝中に起こるため、自覚がないケースも少なくあり
ません。ご家族に歯ぎしりを指摘された方は、歯科での相談をおすすめします。予
防には、就寝時にナイトガード(マウスピース)を使って歯や歯ぐきを保護する方
法が有効です。
⑤矯正治療の影響
矯正治療は適切な力をかけて少しずつ歯を動かしますが、強い力がかかりすぎると、
歯ぐきの位置が下がることがあります。また、矯正中の歯磨きが不十分な場合、歯
ぐきが退縮することがあります。
矯正治療は適切な力をかけて少しずつ歯を動かしますが、強い力がかかりすぎると、
歯ぐきの位置が下がることがあります。また、矯正中の歯磨きが不十分な場合、歯
ぐきが退縮することがあります。
⑥加齢による変化
年齢を重ねると、歯ぐきのハリや弾力を保つコラーゲンやエラスチンが徐々に減少
し、自然と歯ぐきのボリュームが失われることがあります。これは老化の一環とし
て避けられない部分もありますが、毎日の丁寧なセルフケアで歯周病を防ぎ、栄養
バランスの良い食事や規則正しい生活を心がけることで、進行を緩やかにすること
が可能です。歯ぐきの健康を保つには、年齢に応じたケアと予防意識が重要です。
⑦噛み合わせが悪い
出っ歯や受け口、開咬などの不正咬合があると、特定の歯に過度な力が集中しやす
くなります。このような状態が続くと、歯周組織に過剰な負担がかかり、歯周病の
進行を早めたり、歯を支える骨が吸収されやすくなります。その結果、歯ぐきが縮
むリスクが高まるのです。また、噛み合わせの乱れは歯周病の悪化を招くだけでな
く、顎関節への影響や頭痛・肩こりといった全身症状につながることもあるため、
歯並びや噛み合わせに不安を感じた場合は、早めに歯科で検査を受けることをおす
すめします。

矯正治療と歯肉退縮について
矯正治療では、精密な検査と綿密な治療計画に基づき、歯にかける力を適切にコン
トロールして進めるため、矯正自体が原因で歯肉が大きく下がることは稀です。実
際には、矯正中の口腔内の清掃不足により歯ぐきの炎症が起こり、位置が下がるこ
とが多いです。矯正装置の種類に関係なく、常に口腔内を清潔に保つことが、歯肉
退縮を防ぐための重要なポイントです。
◎ワイヤー矯正
ワイヤー矯正では装置の周囲に汚れがたまりやすくなるため、矯正前よりも丁寧な
セルフケアが必要です。磨き残しが続くと歯肉炎や歯周病が進行し、歯ぐきが後退
する恐れがあります。日々のケアでは、小回りの利くタフトブラシやヘッドの小さ
な歯ブラシを活用し、必要に応じて抗菌性のあるマウスウォッシュを取り入れると、
より清潔な環境を保ちやすくなります。
◎マウスピース型矯正(インビザライン)
マウスピース型矯正は取り外しができるため、歯磨きや食事がしやすいという利点
がありますが、一方で1日20時間以上の装着が必要なため、長時間口腔内に密着
する状態が続きます。そのため、装着前に歯をしっかり磨き、マウスピース自体も
清潔に保つことが重要です。これを怠ると、マウスピース内で細菌が繁殖しやすく
なり、歯ぐきの炎症や歯肉退縮の原因となる可能性があります。マウスピースの使
用中に違和感や異常を感じた場合は、早めに歯科医師に相談しましょう。
歯肉退縮を防ぐための日常ケア
毎日のセルフケアの中で、歯肉退縮の予防は可能です。以下のような対策を心がけ
ましょう。
①正しいブラッシング法を身につける
力を入れすぎたブラッシングは、歯肉を傷つける大きな原因です。歯ブラシは鉛筆
を持つように軽く持つと力のコントロールがしやすくなります。小刻みに動かして
歯と歯ぐきの境目をやさしくなぞるように磨きましょう。歯磨きは「力よりもテク
ニック」が大切です。理想的なブラッシング圧の目安は100〜200g程度の軽い力
です。歯ブラシの毛先を細かく動かし、やさしく丁寧に磨くことが、歯ぐきを守り
ながら汚れをきちんと落とすポイントです。歯並びによって磨き方のコツも異なる
ため、一度歯科医院でブラッシング指導を受けるのもおすすめです。
②柔らかめの歯ブラシを使う
特に歯ぐきが敏感な方や、すでに炎症を起こしている場合には、優しく磨ける柔ら
かめの歯ブラシを選びましょう。硬すぎるブラシは、歯肉を刺激しすぎる原因にな
ることがあります。また、毛先が開いたままの歯ブラシを使い続けると、プラーク
の除去効率が悪くなるため、1カ月に1回の交換も心がけましょう。
③喫煙を控える
喫煙は歯ぐきの血流を悪化させ、口腔内を乾燥させることで歯周病のリスクを高め
ます。また、すでに歯ぐきに炎症がある場合には、喫煙の影響で治療効果が現れに
くくなり、症状の改善が遅れる原因にもなります。歯ぐきの健康を保つためにも、
できるだけ喫煙を控えた方が良いでしょう。
④定期的に歯科検診やメンテナンスを受ける
歯肉退縮を早期に発見・予防するためには、プロによる定期的なチェックとケアが
欠かせません。歯科医院では、セルフケアでは届きにくい場所のクリーニングや、
歯ぐきの状態に応じたアドバイスが受けられます。自覚症状がなくても、3〜6カ月
に1回は歯科検診を受ける習慣を持つことをおすすめします。
歯肉退縮を感じたら歯科医院を受診しましょう

歯肉退縮は、見た目の印象を変えるだけでなく、知覚過敏や虫歯のリスクを高める
など、お口の健康にさまざまな影響を及ぼします。原因は加齢の影響だけでなく、
強すぎるブラッシングや食いしばり、不十分なケアなど、多岐にわたります。その
まま放置するとお口のトラブルが起こりやすいため、早期の対処が大切です。毎日
のセルフケアに加え、定期的に歯科検診を受けることで予防や進行の抑制が可能で
す。違和感を覚えたら、早めに歯科医院で相談しましょう。東京八重洲キュア矯正
歯科は矯正のカウンセリングを随時行っております。歯並びが気になる方は、ぜひ
お気軽にご相談ください。スタッフ一同お待ちしております。カウンセリングのご
→予約はこちらから
https://plus.dentamap.jp/apl/netuser/?id=4491&_gaid=1770588889.1637737917






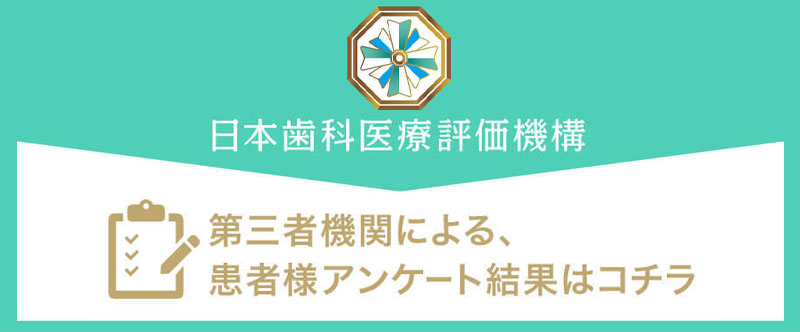
 治療ガイド
治療ガイド