投稿日:2025.8.15
歯科矯正をすると知覚過敏になるって本当?
むし歯でもないのに、冷たい物がしみる症状が出る時は「知覚過敏」の可能性があります。
知覚過敏はいくつか原因があり、めずらしい症状ではありません。
ただし、冷たい物を飲食した時にしみる症状が出るため、日常生活で飲食が苦痛になってしまうことがあります。
歯科矯正を検討している方で「矯正をすると知覚過敏になるの?」と心配されるお声を聞きます。
そこで今回は、歯科矯正と知覚過敏についてお話させていただきます。

目次
知覚過敏とは?

冷たい物を飲んだ時に「キーン」とした場合には、知覚過敏の可能性があります。
通常は、歯の内部の「象牙質」は「歯ぐき」や「歯の表面のエナメル質」に覆われています。
知覚過敏は加齢や歯周病などが原因で、歯ぐきが下がって、象牙質が出ることで起こります。
象牙質には、神経に伝わる「象牙細管」という無数の穴があるため、この部分を通して冷たい物などの刺激が伝わり、知覚過敏の症状となってあらわれます。
ただし、持続的な痛みではなく、冷たい物がなくなると症状が落ち着きます。
知覚過敏の悪循環

知覚過敏の症状が出ると、歯ブラシの圧も痛みとして感じる場合があります。
そうすると、十分に歯垢を落とすことができず、歯周病の悪化やむし歯になりやすくなってしまいます。
さらに、象牙質の部分が出ているところは、やわらかいため、むし歯のリスクも高くなります。
この悪循環にならないように、知覚過敏のケアをすることが大切です。
矯正治療中に知覚過敏を引き起こしてしまう4つの原因
1 歯を動かした時に隠れていた部分が刺激を受けるようになった
歯の内部には、象牙質がありますが、硬いエナメル質で覆われています。
しかし、歯ぐきが露出したり、エナメル質が溶かされたりすると刺激を受けてしみる症状が出る場合があります。
矯正は、適切な力をかけて徐々に歯を動かしますが、一時的に歯と歯ぐきのすき間ができて、その部分がしみてしまうことがあります。
ほとんどが一時的な症状で、徐々に落ちつくことが多いです。
矯正治療をスタートしたばかりの時は、全体的な歯並びを整えるために、適切な範囲で歯を動かす量が多くなるため、しみやすいようです。
2 歯磨きの力が強かった

歯磨きの際の力は、100~200g程度といわれており、強い力ではなく、細かく磨くことが大切です。
汚れを一生懸命落とそうとして、ブラッシング圧が強すぎると、歯ぐきが下がる原因になることがあります。
歯ぐきが退縮してしまうと、その部分は知覚過敏の症状を起こしやすくなります。
歯磨きは、1~2本程度を目安に細かく動かしましょう。
また、鉛筆を持つように歯ブラシを持つと、適度な力で磨きやすくなります。
普段のセルフケアで疑問に思っていることは、定期検診の際にご質問いただくとお答えで
きますので、お気軽にご相談ください。
3 磨き残しがある

矯正でつけるワイヤーと歯の間に汚れが残りやすいので、磨き残しがそのまま放置されて歯が酸で溶かされたり、むし歯になったりして、しみる症状が出る場合があります。
ワイヤー装置は固定されているので、その部分に汚れがつきやすくなります。
クリニックでは、歯磨きの仕方をお話しますが、歯ブラシだけでは汚れが残ってしまいがちなので、1束だけのタフトブラシなどの補助清掃用具を併用しましょう。
また、ワイヤー矯正をしている時でも通すことができる「デンタルフロス」もあるので、歯と歯の間の汚れも落としましょう。
矯正を開始する前には、見えなかった歯の重なり合った部分にむし歯がある可能性もあります。
歯並びが整ってくると、徐々に歯磨きもしやすくなりますので、頑張って歯磨きをしましょう。
4 歯を並べるスペースを確保した時の刺激
歯を並べるスペースが大幅に足りない時には、抜歯が検討されますが、健康な歯を抜歯することに抵抗がある方もいると思います。
歯並びの不正が軽い場合には、歯と歯の間にやすりをかけるようにして、歯を並べるスペースを作る「IPR」という処置があります。
歯の表面のエナメル質の部分だけを削る処置で、0.2~0.5ミリ程度の範囲で0.1ミリ単位に細かく処置をします。
歯の健康に影響が出ない範囲で処置をしますが、処置をした時の刺激で一時的にしみることがあります。
通常は、徐々に落ち着いてきますので、様子をみてくださいね。
矯正中に知覚過敏にならないための2つの対策

1 歯磨きの時に力を入れ過ぎない
先ほども少しお話しましたが、強すぎる歯ブラシの力は歯ぐきが退縮してしまう原因になります。
力を強いと感じる方は、歯ブラシの毛先の硬さも、硬めのものより「ふつう」から「やわらかめ」のものを選びましょう。
また、ヘッドも小さめがおすすめです。
定期検診の時に、正しい歯磨きの仕方や歯ブラシの圧などもお話できますので、お気軽にご相談ください。
2 お口の中を清潔に保つ
ワイヤー矯正は歯と装置の間に汚れが残りやすい環境です。
マウスピース矯正の場合には、取り外しができるので、食事をする時は今まで通り食べられるメリットがあります。
しかし、歯磨きをせずにマウスピースをはめてしまうと、細菌が密閉されて増殖しやすくなります。
お口の中の細菌は空気が少ない所を好む性質があるので、その環境はむし歯や歯周病のリスクを高めてしまいます。
そのため、マウスピースは、歯磨きをして清潔にしてからつけましょう。
矯正期間中にお口の中を清潔に保つことを習慣化すると、歯並びが整った後もお口の清掃環境を整えやすくなります。
いつまでもお口の健康を守るためにも、毎日の丁寧なセルフケアを行いましょう。
矯正中に知覚過敏になった時の対処法とは?

・知覚過敏用の歯磨き粉を使う
歯磨き粉には、さまざまな用途によって成分が異なります。
着色除去を目的としている歯磨き粉には、研磨剤が含まれている場合があり、知覚過敏の方はしみることがあります。
一方、知覚過敏専用の歯磨き粉は、知覚過敏の痛みを抑える成分も含まれていますので、使用することで、徐々に痛みを緩和しやすくなります。
「硝酸カリウム・乳酸アルミニウム」などの知覚過敏の痛みを緩和する成分が含まれているものを選びましょう。
歯磨き粉選びに迷ったら、クリニックでご相談ください。
・クリニックに相談しましょう
クリニックでは、知覚過敏に対応している処置をすることができます。
歯の表面をコーティングするお薬を塗布するケースが多く、患者さまの負担に少ない方法です。
患者さまの状態に応じて対応いたしますので、ご相談ください。
また、知覚過敏になった原因を探って、その原因を改善することも大切です。
そのまま継続していると、再度知覚過敏の症状が出たり、悪化したりする可能性も考えられます。
矯正の調整の際にもご相談いただけますので、気になることは遠慮せずに教えてくださいね。

【まとめ】
知覚過敏にはさまざまな原因があります。
矯正治療をスタートした時に歯のスペースを作る処置をした時など、一時的に痛みを感じる場合がありますが、徐々に落ち着いてきますので、様子を見ましょう。
また、むし歯や歯周病など、矯正とは別の原因で痛みが発生している可能性もあります。
痛みが継続的に続く場合には、早めに相談して、原因を探り、解決していきましょう。
当院では、ワイヤー矯正も表側矯正、裏側矯正、マウスピース矯正に対応しており、患者さまの歯並びとご希望を考慮した上で治療方法をご提案いたします。
歯並びが気になっている方は、カウンセリングでお悩みをご相談ください。





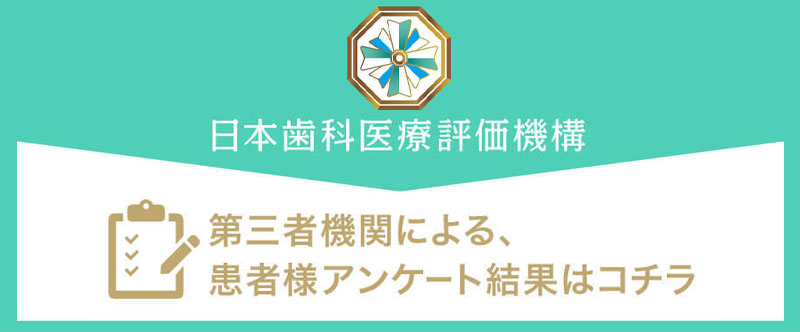
 治療ガイド
治療ガイド